|
|

|
漬け物の代表格「たくあん」に挑戦!!
 |
|
|
|
|
|
|
|
ぬか:適量
砂糖:お好み
干し大根:30? |
|
|
|
 |
■大根はまっすぐで、あまり太くないものが理想です。
■ 太さはできるだけ一定の物を選んでください。
■ 寒風の中で、短期間に乾燥させるのがコツです。
■ よく乾燥した大根を、先に漬け込んでください。
■ 糠は新糠が最良で、フルイにかけて小米を除いてください。
■ 風味付けに、りんご、渋柿の皮、なすの葉などを入れても美味しくなります。ただし3月頃までに食べ上げる物に限り、それ以上永く置く物は、酸味が出るのであまり良くありません。
干し大根(30kg)を使用する場合
|
| 食べる時期 |
干す期間 |
大根の乾燥 |
たくあん漬けの素 |
厚生塩 |
ぬか |
| 1〜3月 |
10〜12日 |
“へ”の字 |
1袋 |
1kg |
2kg |
| 4〜6月 |
14〜15日 |
“つ”の字 |
1袋 |
1.5kg〜1.7kg |
1.3kg |
| 7月以降 |
20〜24日
|
“の”の字 |
1袋 |
2〜2.5kg |
1kg |
厚生塩は塩分ひかえめの体に優しいタイプの塩ですが、一般的な食塩を代用いただいてもかまいません。その場合は、厚生塩と同じ分量をご利用下さい。
・厚生塩、お好みで加える砂糖の量は、気候、好みなどにより加減してください。
・甘口を好まれる方は砂糖を追加してください。
|
|
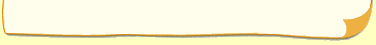 |
大根は傷を漬けないように軍手などで、丁寧に洗います。
ヒゲ、シッポもそのままにして下さい。
|
干す前に芯葉を取り、日が当たる場所よりも、風が通る場所を選んで干します。
☆芯葉とは中心の短い葉のことです。
☆干し時間は上記表を参照して下さい。 |
干しあがった大根は、葉を1〜2センチ残して落とします。
葉は後で必要なので、別にしておきます。
☆大根に傷をつけないことが大切です。
固めになった大根は、まな板の上で両手で押しながら転がし、柔らかくします。
|
容器の底に混合した素を軽く振り、大根を隙間の無いように、頭と尻を交互に並べます。
隙間が出来た時は、干した葉を詰め込みます。 |
一段毎に素を振り、二段目、三段目も同じ向きに並べます。
☆大根は、井桁にならないように並べます。井桁に並べると隙間が多くなり、水上がりが遅くなります。 |
| 一番上に素を多目に振り、干した葉で全体を覆います。 |
45kg程の重石をします。
漬け液が上がったら重石を30kg程にします。
40〜50日頃より食べられます。
☆食べるときに取り出した大根の隙間は、干し葉を詰め空気に触れさせないことが、美味しさを保つコツです。
|
 
|
干してしまえば二度漬しなくても良いので、意外に簡単です。
麹漬けと同様、こちらも体力仕事ですね。
「漬け物時は嫁逃げる」とはよく言ったものです。大忙しです。
でも漬けてしまえば、漬けあがるのを待つだけ。なんだか楽しみですね♪
評価:★★★★★ |
|
|
|