|
|

|
動画でCHECK!!
厚生塩を使った
美味しい梅干しの作り方
 |
|
・完熟梅(1) 2kg
・塩(2) 400g
・しその葉(3) 600g
・しその葉用塩 100g
・ボウル
・保存用容器(4)
・3〜4kgの重石
・ざる
・竹串 |
|
|
|
 |
梅干にする梅は黄色くなって香りがあり、柔らかくなった完熟のものが最適です。
減塩で漬ける場合は、塩200gとホワイトリカー1カップを用います。減塩タイプなので塩辛さは抑えられますが、カビが生えやすくなるので注意が必要です。
しそはひと束で250gくらいの葉がとれます。
梅の酸に負けないように、陶製のカメやホーロー鍋が良いです。
【カビが生えてしまった!】
下漬中:
梅を取り出しボールに入れホワイトリカーで洗い、天日でしっかり乾かします。白梅酢はホーロー鍋に入れてアクを取りながら煮立てて冷まします。容器はきれいに洗って熱湯消毒し、乾いてから漬け直します。
本漬中:
梅はボールに入れホワイトリカーで洗って天日で乾かします。赤しそも同様にします。赤梅酢はホーロー鍋にいれてアクを取りながら煮立てて冷まします。容器はきれいに洗って熱湯消毒し、乾いてから漬け直します。
一度カビが生えると、処置をしてもまたかびやすくなります。漬け込み中は時々様子を見て、カビが生えてきたようなら、すぐに処置をするようにしましょう。 |
|
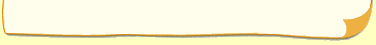 |
梅を一晩水に漬けてアクを抜きます。(赤く完熟した梅は水洗いだけで大丈夫です。)
水切りをし、梅のへたを竹串で取ります。
清潔な布巾で水気をていねいに拭き取ります。 |
用意した塩の半分の量(200g)と梅を良く混ぜます。
(減塩の場合は100gとホワイトリカー1/2カップをと梅を良く混ぜます。)
熱湯消毒した容器に、3の梅と残りの塩を交互に漬け込みます。
塩にホワイトリカーを少し混ぜておくと塩が容器の下に落ちていかないので効果的。殺菌作用もあります。
(減塩タイプの場合は、3の梅と残りの塩とホワイトリカーを交互に漬け込みます。)
落し蓋をし、3〜4kgの重石をのせます。1〜2日で水が上がってきます(これを白梅酢といいます)ので、重石を半分に減らします。このまま10日以上冷暗所で漬け込みます。 |
しその葉を水洗いし、よく水気を切ります。水気が残っていると塩もみのときアクが取れにくくなります。
しその葉に塩を半分(50g)振り、しんなりしたら強く揉んでアクを出します。出たアクは捨てます。
もう一度、残りの塩を加えてよく揉み、きつく絞ってアクは捨てます。
5で上がった白梅酢100ccをかけ、赤く発色するまでほぐすように軽く揉みます。
残りの白梅酢は梅がかぶる程度まであればよいので、余ったものは熱湯消毒したビンに入れて保存しておけば、漬物や料理に使えます。
揉んだしそを梅に平らに隙間なくのせ、赤い汁も加えます。
重石は梅に汁がかぶるくらいの軽いものをのせ、土用(7月20日頃)まで保存します。上がってきた汁を赤梅酢といいます。 |
土用の晴天が続く日に、3日間梅を干します。
日中に一度梅を裏返し、夜は赤梅酢のある容器に戻します。
梅を干す際に、赤梅酢も容器ごと日に当てると赤色が濃くなり、また殺菌にもなるので良いです。
最後の日に梅を取り入れ、梅がさめたらきれいに洗って消毒した容器に入れて保存します。この時、梅に酒を振りかけておくとカビ防止になります。
しそは梅と同じ容器で保存すると梅が黒ずむので別けた方が良いでしょう。 |
|
|